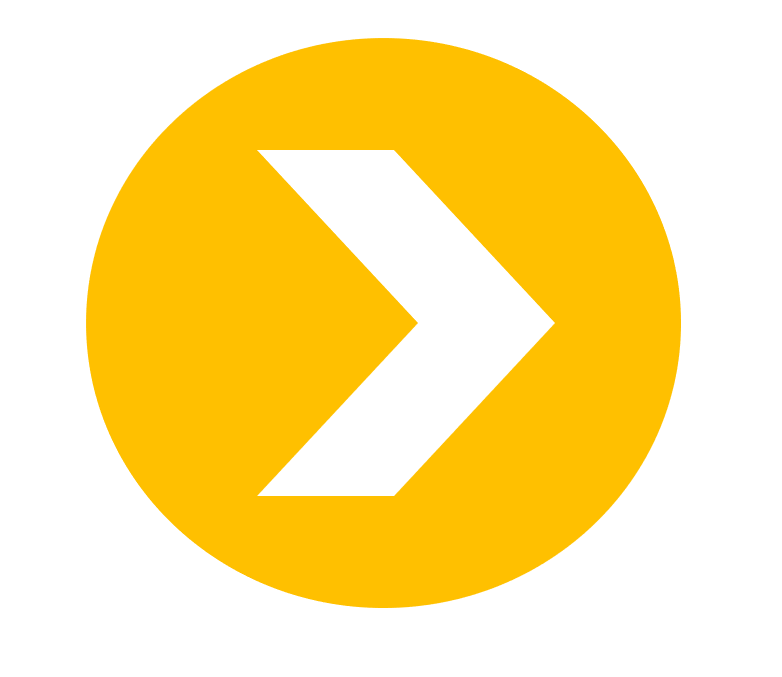フランチャイズで成功する!
ハウスクリーニング独立開業の第一歩
開業時に記入する「屋号」とは
「屋号」とはなにか
「屋号」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。開業届には確定申告書に「屋号」を記入する欄があります。この言葉の意味を理解していないと独立後にこれらの書類を提出するとき困ることになるでしょう。
今回は独立開業したときに困らないようにするために屋号について解説していきます。
屋号とはどういったものを指す?
屋号とは会社名の代わりに個人事業主が付けられる名前のことです。基本的に個人事業主は、個人名を使用して活動していくことになります。しかし、店舗を構えるときなどには個人名以外を付けたいものですよね。
他にも事業の内容によっては個人名を出すことに抵抗を覚える人もいます。これらの理由以外にも、お店に別の名前を使いたいと感じることは多々あるでしょう。開業届を出すときに屋号を付ければ、自分の名前を使えるのです。
屋号は必ずつける義務があるか?
個人事業主となり独立したからといって必ずしも屋号をつける必要はありません。開業届や確定申告書に屋号の欄があるため、必ず記入しないといけないと思ってしまいがちですよね。しかし屋号を付けるかどうかは個人に選択肢がありますので、空欄のまま提出しても問題ありません。
また後からでも屋号は付けられるものです。もし個人名だけでも事業を展開できるなら、屋号を付けなくても開業できます。
屋号をつけるメリット
店舗を経営するなら、店舗名を屋号にするのが一般的。士業の事務所や病院も多くのケースにおいて事務所名や病院名を屋号とします。ライターやイラストレーターの場合は、ペンネームを屋号とすることも。一方オフィスを設けずに事業を展開できるアフィリエイターは、無理に屋号をつけなくてもいいでしょう。
屋号をつけることによって事業を経営していくうえで便利となることがあります。それは銀行口座の名義に屋号を入れられることです。続いて屋号を銀行口座にできることのメリットについて解説していきます。
屋号付き銀行口座のメリット
まず銀行の口座をプライベート用の口座と事業用の口座をハッキリと区別することによって、経費や売り上げの管理が容易となるでしょう。また経費と売り上げの流入の確認が容易になるため、確定申告書の作成も楽に。他にも印鑑や名刺に屋号が入っていると、事業として活動していることが印象的になるので社会的な信用を得やすいともいえます。
また屋号をつけると取引相手・顧客に覚えてもらいやすいというメリットを挙げられます。フリーランサーなどは個人名で営業しても問題ないかもしれませんが、店舗経営者が個人名で営業をするとお店の名前を覚えてもらえない可能性があります。開業をする前にちゃんとしたコネクションを取引先や見込み客と築けていれば問題ありませんが、0からスタートするなら屋号をつけて覚えてもらうことから始めるといいでしょう。
口座を作る際に必要な書類
屋号付き口座を開設するときには書類や証明書などを提出する必要があります。
最初に必要となるのは本人確認書類となる運転免許証やマイナンバーカードなどと印鑑。次に屋号確認資料が必要です。開業届では事業を経営していることの証明となります。屋号確認資料には、税金の納税証明書や領収書、事務所オフィスの賃貸契約書、公共料金の領収書などがあります。
口座開設の際に提出しないといけない書類は金融機関ごとに異なるケースがありますので、事前に確認しておくといいでしょう。
屋号登録の仕方・方法
屋号登録の仕方は簡単ですので、難しく考える必要はありません。
屋号は開業届に屋号を記載して税務署に登録するだけ。屋号に法的効力を持たせたいならば、法務局で登記手続きを済ませましょう。これを商号登記といいます。商号登記をしておけば屋号で銀行口座を開設したい場合に、屋号名義での口座開設が通常よりも簡単になるメリットがあります。
他にも特許庁で商標登録をしておけば、日本のどこであっても同じ商標を登録することができなくなります。この商標登録の場合は屋号などの名称を商品名につけるためのものなので、ブランド力のある商品を出したいと思っている場合は登録をしておくことをオススメします。他にも商標登録をしておけば屋号がかぶる可能性が減少するので、安心です。
屋号をつけるときの注意点
屋号はある程度自由に付けられます。しかしいくつか制限があります。また、事業の成長に効果的でない屋号もあるので、気を付けましょう。
使える文字
屋号をつけるときに使える文字は漢字、ひらがな、カタカナ、数字、ローマ字と一部の´です。
使えない言葉
「会社」や「法人」など法人を表現する文字(言葉)を用いることはできません。このふたつ以外にも、「○○証券」や「○○銀行」といった特定の業種でなければ使用を認可されていない表現もあるので注意しましょう。
アルファベットを使う際は気を付けて
アルファベットなども使用可能ですが、あまり独特な名称は避けたほうが無難です。電話などを通じて口頭で屋号を伝えた際に分かりにくいといったデメリットがありますし、記入をした際に分かりにくいといったこともありえます。
また日本なら、サインではなく押印する機会があります。その際にアルファベット表記では読み取りにくいといったデメリットも予測できます。
同じ屋号が地域周辺にないか
使用できる文字、名称で屋号の候補を決めたら次は同じ屋号が登記する地域の周辺にないかをチェックしましょう。商標登記されている名称ならば、法務局を利用すれば調べられます。同じエリアで業種や屋号がかぶってしまうと、かぶってしまった相手にも迷惑となりますし、取引先や顧客にも混乱を生じさせてしまいます。そのため屋号を決める際は、同じ屋号が周囲に存在していないかを確認するようにしましょう。
また、似たような名前が多い屋号だと、会社のことを調べたくても調べられないという状況に陥るので注意が必要です。例えば、「スマイル」という単語を使った屋号は多数存在しています。せっかくお客さんが興味をもって調べてくれても、別の会社ばかりが出てしまい、顧客獲得のチャンスを失う事態になってしまうのです。
インターネットで調べた際に表示される可能性が高いか
インターネットで検索した際に上位表示される名称なのかも確認したほうがいいでしょう。屋号でも上位表示がとれると、店舗や事業の認知度がアップします。
長すぎないか
屋号の名前に長さの制限はありません。しかし、あまり長すぎて覚えにくいもののはオススメしません。長くても略して覚えられるものなら問題ありません。
長すぎると、屋号を覚えてもらえない・SNSや口コミサイトで発言されにくいなどのデメリットがあります。事業はお客様に存在を覚えてもらうのが第一。名前が長すぎて客足が遠ざかっては元も子もありません。
また、印鑑をつくる際にもバランスが悪くなってしまうため、適度な長さにしましょう。
屋号の変更はあとからでも可能
可能な限り変える必要のない屋号を始めにつけることが望ましいですが、どうしても変えたい場合に屋号を変えられます。実のところ屋号は税務署へ屋号の変更届などを出さなくても変更することが可能です。屋号変更方法は、確定申告時に申告書や決算書に変更したあとの屋号を記載して出すだけです。
ですが、屋号を変更した証拠を記録として残しておきたいと思う人は、開業届を再提出する方法もあります。したがって、独立・開業をしたあとに事業内容が変わり屋号と合わなくなってしまった場合は、屋号の変更をすれば問題ありません。しかし、せっかく覚えてもらった屋号を顧客や取引先に覚えなおしてもらうリスクがあることを理解しておきましょう。
屋号についてまとめ
結論、屋号をつけることは法的に大きな役割を果たしていません。しかし、屋号を軽く見てあまりいい加減な名称をつけるとあとになって後悔する可能性があります。顧客への印象や取引先に覚えてもらうなどの役割を屋号は担っているので、そこを軽視するのはよくありません。あとからでも屋号は変えることができますが、そうなった場合には顧客、取引先に屋号を覚えなおしてもらうといったデメリットがあります。
もし、屋号を変更する際は取引先にだけでも迷惑がかからないように連絡やお知らせをするのが礼儀と言えるでしょう。
関東のみといったエリア限定ではなく「全国」で開業可能で、初心者でも安心して始めることができる研修制度を設けているフランチャイザーを開業資金・ロイヤリティが安い順に3社紹介。
※2021年10月時点の調査情報を元に作成しています
| ハウス コンシェルジュ |
おそうじ本舗 | おそうじ革命 | |
|---|---|---|---|
| 初期 費用 |
268.7万円 | 333.5万円 | 381万円 |
| 公式 サイト |
※2021年10月時点の調査情報を元に作成しています
| ハウス コンシェルジュ |
おそうじ本舗 | おそうじ革命 | |
|---|---|---|---|
| 初期 費用 |
268.7万円 | 333.5万円 | 381万円 |
| 公式 サイト |
開業資金の合計が安い順に3社紹介。
※2021年10月時点の調査情報を元に作成しています
![[頑張った分きちんと稼げるのはどこ?]ハウスクリーニングフランチャイズ独立開業ガイド](https://www.ieclean-fckaigyou.com/wp/wp-content/themes/wp001j/img/head_ttl.png)